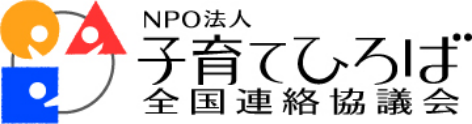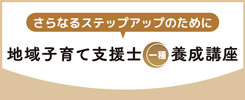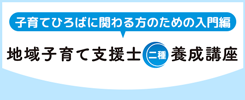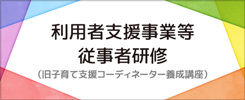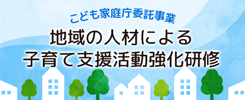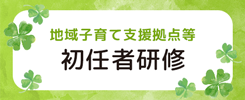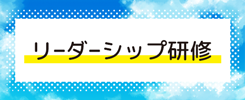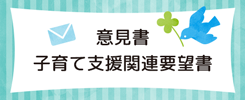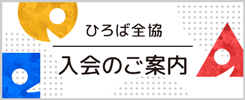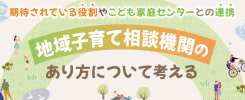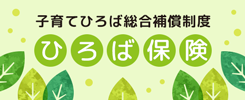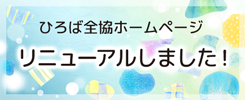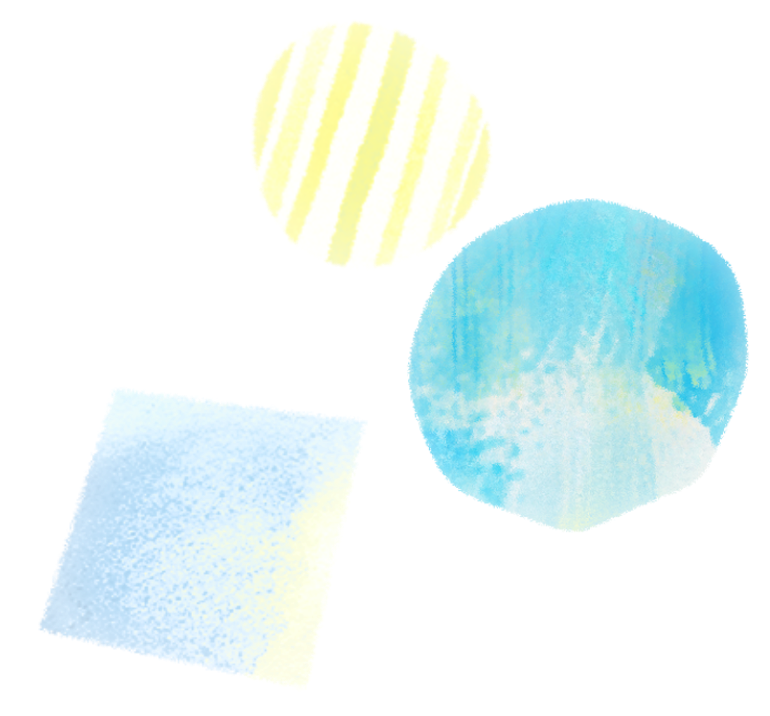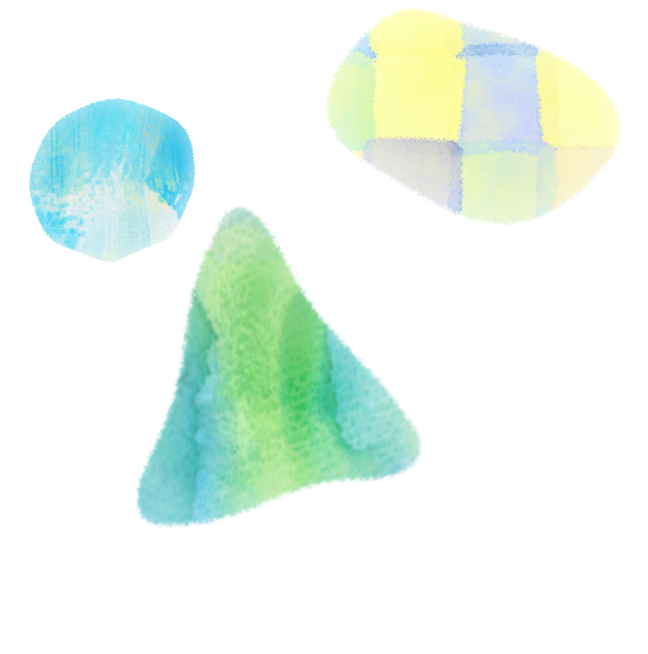
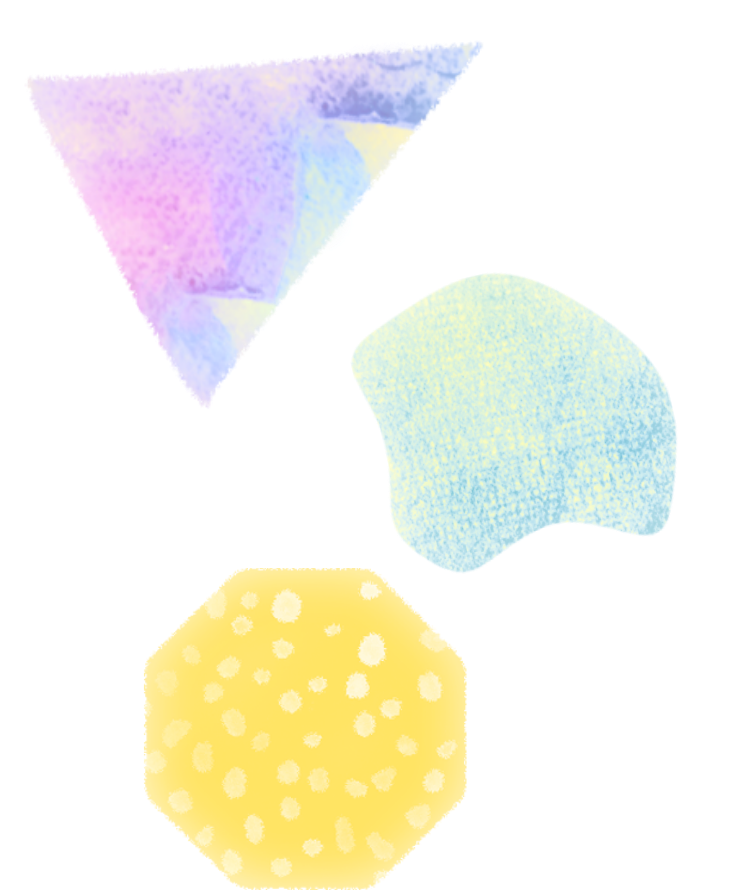
NEWSお知らせ
-
- 申込受付中
- 2024-05-01 2024年度地域子育て支援士一種申込受付中
-
- 申込受付中
- 2024-05-01 2024年度初任者研修申込受付中
-
- 申込受付中
- 2024-05-01 2024年度利用者支援事業等従事者研修受付中
-
- 申込受付中
- 2024-05-01 2024年度地域子育て支援士二種養成講座申込受付中
-
- 申込受付中
- 2024-05-01 2024年度リーダーシップ研修申込受付中
-
- 申込受付中
- 2024-04-16 地域子育て相談機関のあり方について考えるフォーラム
-
- 申込受付中
- 2024-03-27 2024年度地域の人材による子育て支援活動強化研修
-
- 申込受付中
- 2024-03-25 利用者支援専門員(基本型)のひろばのご案内
-
- 申込受付中
- 2024-03-19 2024年度プレママ・プレパパ向けの講座のためのワークショップ申込受付中
-
- 申込受付中
- 2024-03-19 2024年度テーマ別交流会申込受付中
-
- 申込受付中
- 2024-03-19 2024年度予防型プログラム研修申込受付中
-
- 申込受付中
- 2024-02-25 2024年度公開セミナー申込受付中